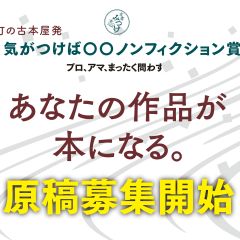【講評】[加藤正人&倉田真由美&本橋信宏]第2回「気がつけば○○ノンフィクション賞」最終選考

第2回「気がつけば○○ノンフィクション賞」は、先週末の記事にてお伝えしたとおり、「受賞作なし」となりました。
ここでは、「受賞作なし」の理由も含めて、最終選考にたずさわっていただいた3人の審査員の方々による講評を公開いたします。作品を書いた著者の方々だけでなく、これから第3回目の応募を考えようと思っている方や、当文学賞だけでなく、何かを書いていきたいと考えている人にとっても、たいへん参考になる講評ですので、ご一読いただけたら幸いです。
加藤正人(脚本家)

2024年公開の「碁盤斬り」は、加藤先生の書き下ろしによる小説が原作。そして自らが脚本に起こした映画も大ヒット。
今年も、選考の審査を引き受けることになった。
今年の最終選考には、結芽かえでさんの「気がつけば医療的ケアの母になっていた。」、オリエンタル納言さんの「気がつけば保育の世界で死にかけた。~もしくはマッチングアプリ女子の極私的物語~」、生天目安昭さんの「気がつけば親の生き方に囚われていた。」の3本が残った。
結論から言うと、3本ともに出版には至らずという結論になった。それぞれ、作者の思いは感じられるものの、作品としてはまだ未熟な印象を受けた。
エドワード・モーガン・フォースターというイギリスの小説家がいる。有名な小説家だが、「ハワーズ・エンド」、「インドへの道」、「眺めのいい部屋」、「モーリス」など、映画化された作品が多いので、映画ファンにも原作者として名前が知られている。
彼は、時系列に沿って出来事を並べていけばストーリーになるが、それだけではいけないという文章を残している。
単なるストーリーではなく、これからどうなるのかと、読者に展開を期待させるようなものでなければならないのだ。そのためには、それぞれの出来事が、因果関係で結ばれているプロット(企み)が必要であるということも述べている。
Aという出来事があれば、その次に起こるBという出来事は、Aのリアクションとして引き起こされるようなものでなければならない。Aという出来事が起こり、〈だから〉Bという出来事が起こったというように、有機的にエピソードが繋がっていくことを考えるべきだと主張している。
これは小説の書き方のための理論だが、エッセイや論文の執筆にも応用できる考え方だ。
私は脚本家だから、出来事が有機的に繋がっている〈プロット〉ということを、常に強く意識しながら物語を作っている。
どうしてこのような前書きを書いたかというと、書籍というものは著者が自分の思いを伝えるものであるのだから、読者を作品の世界に引きずり込むような面白さが必要になるということを言いたいからだ。作品を書くには、読者の気持ちを掴み、感動的な結末まで引っ張っていくという計算が必要になる。ノンフィクションであれば、必要でない部分はそぎ落とし、どのような切り口で流れを作るかということに腐心することになる。
そういった文脈の作り方が、3作品ともに稚拙であった。
「気がつけば医療的ケア児の母になっていた。」
結芽かえでさんの「気がつけば医療的ケアの母になっていた。」は、多発性小腸閉鎖症という難病を抱えて生まれてきた長女との壮絶な闘病を描いた作品だった。本来ならば長男に続いて長女が誕生して幸せな家族生活が始まるはずが、難病を抱える娘の誕生によって、大変な苦労を抱え込むことになった様子が描かれている。長女の闘病と育児のために仕事を辞めなければならず、次々に困難が襲いかかる。そんな過酷な生活が淡々と綴られてゆく。ことさら運命を呪うでもなく、厳しい現実に懸命に対応する筆者の誠実さが伝わってきた。
特に、児童相談所によって娘と引き離されることになってしまう部分からは、筆者の苦汁がよく伝わってきた。
カテーテル感染で4歳10か月で娘が亡くなり、亡骸を自宅に運んで家族が一つ部屋で眠るという描写には涙を禁じ得なかった。
今回、私はこの作品が最も好きだった。
短い一生であったが、娘が家族に遺してくれた大切なものも、作品から感じられた。
しかしながら、筆が足りない。自分のことだけでなく、夫や長男といった家族のことはもっと深く描いたほうがいい。父親もまた、筆者と同様の悲しみや苦しみと闘ったはずだから、そこを書き込んでいけば更に強いドラマになる。
そういう方向でブラッシュアップされれば、いい作品になっていただろう。とても惜しい。
残りの2作品は、結芽かえでさんの作品と反対に、あまりにも文章が長過ぎて冗漫な印象を受けた。
「気がつけば親の生き方に囚われていた。」
生天目安昭さんの「気がつけば親の生き方に囚われていた。」もまた、膨大な人生を描いた作品だった。
両親との確執が延々と描かれているが、これも展開に乏しい親子関係が続いていくだけなのでいささか食傷気味になった。
筆者にとっては両親は身近な存在だが、読み手にとっては全くの他人である。だから、両親については、もっと詳しく描写をしなければ人物像が伝わらない。これほど膨大な文章を費やしても、私には両親のキャラクターがぼんやりしたままだった。もっとディティールを丁寧に描いて欲しかった。
ずいぶん後半になって、自分が神経質過ぎるということに気づき、読書という趣味を通じて同好の士との交友が始まるが、その辺りだけを大切に描けば作品としてのまとまりができていたろう。
「気がつけば保育の世界で死にかけた。」
オリエンタル納言さんの「気がつけば保育の世界で死にかけた。~もしくはマッチングアプリ女子の極私的物語~」は、過酷な保育士の世界とマッチングアプリで出会う男たちというふたつの世界を描いた作品だった。
延々と自分の人生が描かれているが、陰険な保育士やダメな男のエピソードは、同じようなことが繰り返されているようで、読んでいて退屈してしまった。
大長編だが、1本の作品にするなら、もっとテーマを絞り込む必要がある。
この作品では、男たちに絶望し精神の限界に達して保育士としても追い詰められていく筆者が、最後に初めて自分を理解してくれる恋人と巡り会うという展開になる。この男性のおかげで、前向きに生きていけるようになる。この短いパートだけに限定すれば作品としてのまとまりができる。仕事と男性関係で疲弊しきった女性が、精神に深い傷を負いながらもどん底から這い上がっていくという過程を深く描けば、感動的な作品になるだろう。
簡単ではあるが、以上が今回の私の講評である。
残念ながら出版には至らなかったが、今回最終選考に残った3名の筆者には、ぜひこれからも執筆し続けていい作品を発表してもらいたい。次回作に期待している。
倉田真由美(漫画家)

芸人のさかまきさん原作による介護漫画「お尻ふきます!!」。「気がつけば認知症介護の沼にいた。」の著者・畑江ちか子とトークイベントも実施。
「だめんず・うぉ~か~」を描いている時、「現実に起きたことの面白さは、想像を遥かに凌駕する」と確信しました。頭で考えただけでは到底辿りつかない、突拍子のなさ、意外さ、そしてつらさ、苦しさ。必ずしもハッピーエンドならないのだけど、それが人生の醍醐味でもあります。
どの作品もずっしりと重く、「軽々と読める」という類の物語ではなくて、読了するのにかなり時間がかかりました。
誰もが自分の人生に一冊だけ書ける、渾身のノンフィクションを預かる一人になれたことを光栄に思います。
「気がつけば医療的ケア児の母になっていた。」
生まれた時から医療的ケアが必要な子どもを持つということは、親になる誰もが想像することではあるけど実際に皆が体験するわけではありません。精神的、肉体的、金銭大変さは程度によりますが尋常ではないはずです。そして今自分に関わりがないとしても、将来、自分の家族や子孫がその当事者になる可能性は常に否定できません。
だから、知りたい。小さな身体に、どんなことが起きるのか。家族がどうなっていくのか。
それを教えてくれるのが、苦しい中実体験を綴ってくれる本書です。子供の名前を仮名すら使っていない等、かなり客観的に書かれているように思えました。ただこういう作品は、思い切り主観的、感情的に書かれることでより伝わるものもあります。読む側は書き手の感情の発露を受け入れる準備をしているので、もう少し剥き出しの感情をぶつけて欲しかった気もします。
とはいえ抑制された書かれ方で、最後まで重くなりすぎずに読めました。
「気がつけば親の生き方に囚われていた。」
圧倒的な熱量。
書きたくて書いたのか、書かざるを得なくて書いたのか分かりませんが、猛烈な熱量をもって文章を紡いだことがビリビリ伝わってきます。こういう、支配的な親のご家庭で育ちそれに囚われた子は、大人になっても親離れできないこともままあります。よく脱出した!と拍手したい気持ちになりました。
これを吐き出せたことで、親との関係はひと段落したと言えるのではないでしょうか。誰かが読むための物語というより、作者本人の人生の総括のために必要だったという側面が強い物語ではあります。
「気がつけば保育の世界で死にかけた。」
過酷な保育士の環境はいろいろと聞こえてきますが、その中でも相当しんどい職場にいた作者の体験談。
私も子どもを保育園、幼稚園に預けていた経験がありますが、内情に関してはほとんど関知することなく通り過ぎただけだったことを痛感しました。システムの問題もさることながら、やはり「人」。先生同士という少人数の中でうまくやっていくには、問題人物がいると途端に困難が増します。
作者が遭遇した問題人物、よくいるタイプではあるけど自分の「上司」として出会いたくない人たちでした。そのせいで、過重労働というシステム以上に職場が地獄化していくのが伝わりました。
ただ現実の辛いところで、上司の意地悪に救いがないのが読んでいて苦しくなります。個人的には間に挿入されるマッチングアプリ等で出会った男性とのやりとりの箇所が大変面白く、こちらをメインにした方がいいのでは? と思ってしまいました。
本橋信宏(著述家)

毎年何冊もの著作を出版し続ける本橋先生。「歌舞伎町アンダーグランド」を筆頭とした、町歩きアンダーグランドシリーズが好評。
「気がつけば医療的ケア児の母になっていた。」
<娘と過ごした4年10ヶ月の記録>という圧倒的な存在感である。
記録することは娘と自分への最大限の救済であった。
次々と病が襲ってくる。
「あかちゃんの腸が閉塞しているかもしれない」
私自身、3歳のときに腸閉塞で緊急入院したことがあり、身につまされる。
「天国では、もうおにぎりを食べたのかな? 食べられているといいな」
哀切極まる語りである。
惜しむらくは、4年10ヶ月すべての時間に対して、平等にスポットを当てたために、全体がフラットになり、感動が薄まったことだろう。
対象への取捨選択が望まれる。
「気がつけば親の生き方に囚われていた。」
親との関係は子にとって悩ましい問題である。
ほとんどの親子の間で横たわる問題であろう。
殺人事件の半数近くは身内で起きる、とされるほど、こじらせると取り返しのつかないことになる。
本作の著者は38年の人生において親子関係の重圧に悩まされてきた。
それでも著者は前向きである。
みずからテレビ出演を望んだり、タッチフットという競技に熱中したりする。
「私の気持ちを文章化することで、今までモヤモヤしていたものを吐露できる」ということで、本作が完成した。
大作である。
その一方で、今回の他の入選作同様、すべてのエピソードを平等に扱ったために、印象がかえって薄まってしまった。
やはり取捨選択、色彩の濃淡をつけるべきだろう。
「気がつけば保育の世界で死にかけた。」
オリエンタル納言というケレン味あふれるペンネームがいい。
文体も読みやすい。
「たった6人の保育士が120名以上の子どもたちを相手に、フラフラになりながら駆けずり回って」いる職場は、さぞや消耗するだろう。
「小さい頃から挨拶が何より大事だと家庭でも、学校の部活やクラブ活動でも教えられてきました」という著者は、就職の初日に元気よく挨拶するのだが、白い目で見られてしまう。
辛いなあ。
挨拶しても返ってこないと、気持ちが落ち込む。
人間にとってもっとも辛いことは。自分の存在を無視されることである。
挨拶が返ってこないことは、自分の存在を無視されたことなのだ。
「子どもたちにマイスプーンを持ってきて一列に並んでもらい、そこで1口ずつ口に運んでは次の子へ、口に運んでは次の子への繰り返し。まるでヒナの餌やりのような手法」
リアルな職場の実態。
全編にわたり、次々とハプニング、トラブルが降ってくる。
エピソードがてんこ盛りになったために、かえって印象が薄まってしまう。本作も、濃淡の付け方、シーンの取捨選択があれば、さらに読み応えがあったはずだ。
編集部より
以上が、最終選考員の3人からのメッセージです。
冒頭に紹介させていただいた加藤正人先生の「物語の作り方」は、今も最前線で活躍する脚本家ならではの視点で、編集部としてもとても参考になるお言葉でした。「読者を作品の世界に引きずり込むような面白さが必要になる」、そういった視点をもって、今後の応募作を読んでいけたらと思っています。
皆様、ステキな講評をありがとうございました!
そして、前回の記事でもお伝えしましたが、第3回目の公募ももちろん実施予定です。
たくさんの応募作品を集められるよう、さまざまなプロジェクトを考えておりますので、引き続き、「気がつけば○○ノンフィクション賞」も応援いただけたらうれしいです。
最後に、最終選考に残った3人の著者と、第2回に応募してくださった方々に、この場を借りてもう一度、御礼を申し上げさせていただきます。本当にありがとうございました!