【講評まとめ】加藤正人&新井英樹&本橋信宏「第1回古書みつけ(気がつけば○○)ノンフィクション賞」最終選考

第1回「古書みつけ(気がつけば○○)ノンフィクション賞」、栄えある最優秀作品として選ばれたのは、忍足みかんさんの「気がつけば生保レディになっていた。」に決まりました。すでに、最終選考にたずさわっていただいた3人の審査員の方々による講評はそれぞれに発表いたしましたが、ここに1本の記事としてまとめておきたいと思います。
加藤正人(脚本家)
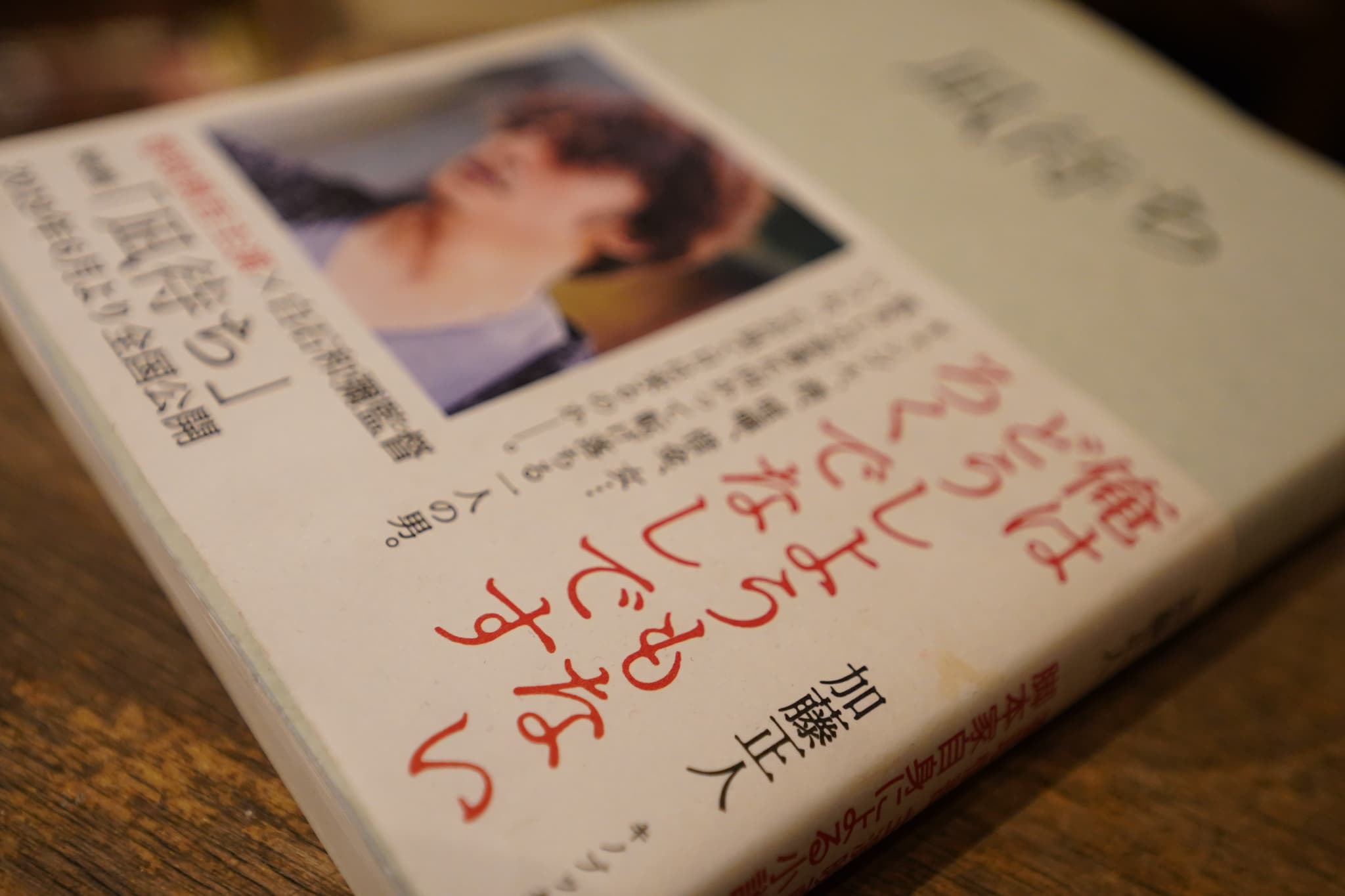
自分のことを書けば、誰でも一本は傑作が書ける。
これは、偉大な脚本家新藤兼人の言葉だ。
誰もがドラマチックな人生を生きている。その人の人生は、その人自身が一番良く知っているのだから、それを書けば素晴らしい作品になるという格言だ。
今回読んだ四本の作品も、それぞれ自分のことを書いている。だから、それぞれに面白さがあった。
真実は重い。それぞれの作品には、なるほどと唸るようなリアリティがあり、心の痛みや、時にクスリと笑わされてしまうようなユーモアがあった。
ストーリーや文体に、完成されていない未熟さもあったが、それ以上の魅力を感じた。
「気がつけば浅草最後の映写になっていた。」荒島晃宏
荒島晃宏さんの「気がつけば浅草最後の映写になっていた。」は、浅草から映画館が消える様子を描いた作品だった。歴史の一ページを記録するという意味でも意義がある。
私は映画の脚本家なので、特にこの作品に惹かれた。
もっとあざとく感動させることもできたかもしれないが、事実を優先してことさらストーリーを加工しないというのが作者の思いであったと思う。職場である映画館がよく描写されていて、懐かしい気持ちになった。
興業のためにあれこれと知恵を絞る映画館の様子には、従業員の皆さんの映画愛を感じて嬉しい気持ちになった。
また、観客の描写もとても面白かった。
シネコン以前の昔ながらの映画館が、浅草という土地柄と相まってとてもいい雰囲気の作品になっていた。
「気がつけば無職になっていた。」薫
薫さんの「気がつけば無職になっていた。」は、コールセンターのオペレーターという仕事の過酷さを描いた作品だった。
会社での仕事の様子が克明に描写されていて、リアリティを感じた。
『誰も僕におっぱいを見せてはくれない』という文章には、思わず笑ってしまった。シャープないいフレーズだ。
主人公のプライベートな生活の様子は、もう少し読んでみたかった。また、家族との関係も面白く読んだ。お見合いのエピソードもたいへん面白かった。その辺りを、もっと書き込んでも良かったような気がする。
文章は丁寧に書かれていて、とても読みやすかった。筆力のある人だと思った。
「気がつけば三十九年間無職だった。」難波ふみ
難波ふみさんの「気がつけば三十九年間無職だった。」は、幼年期からの自身の歴史を描いた作品であった。家族や友人との関係で精神的に追い詰められていく描写には胸が締め付けられた。だが、高校に入学してからは、希望を感じるような展開になった。しかし、現実はフィクションの物語のように都合よくは進まず、病気と格闘しながらの生活が続いているようだ。
この作者は、自分自身を客観的に見つめながらこの作品を執筆したと思う。貴重な体験であったのではないだろうか。
病と付き合いながら、少しずつ克服し、いつか職業について欲しいと思う。その時はぜひ、第二作を書いてもらいたい。
「気がつけば生保レディになっていた。」忍足みかん
忍足みかんさんの「気がつけば生保レディになっていた。」は、物語の舞台となる保険業界の描写に、体験した本人でなければ書けないリアリティさがあった。ノルマに追われる営業職の過酷な労働環境と、適応できずに追い詰められていく主人公の様子が良く描かれていた。職場以外の友人関係についてをもう少し深く書き込んでもいいのではないかという気もした。
文章は現代的なタッチで、若い人たちに支持される文体だろうと思った。弾んだタッチのテンポのいい文章を書ける人だと感心した。
脚本家・加藤正人
新井英樹(漫画家)

物語として表現をする際に、登場する人間をどれだけ大事に扱っているか書き込んでいるかによって、主人公が生きる場・社会・世界が見えてくるし、主人公がそれらをどう見ているか・見られているかが浮き彫りになっていく。
自分が生業にしてる漫画に限らず小説・ドラマ・映画に対しても掲げるテーマや社会的な意義よりも、描かれる人物の生き方・息遣い・体温に触れた!と思えることが重要で、なにより他者である脇の人物の描写こそ想像力の賜物、書き手の創造の源泉だとも思ってます。
個人的に……テーマや意義が主体の物語はキャラがそのための役割セリフを当てられ過ぎて作者の操り人形になって、その大半を忘れちゃうことが多い。でも、いいキャラだけは記憶に残るんですよ。
ただ意図された難しいことも、何かの折に血肉になってたことがわかる瞬間があるととんでもなく嬉しいんですけどね。
これまでは誰かが表現したものを「審査」するなんて……って立場でいたんだけど、今回は実在のいいキャラ・友人の中村京子さんからの声かけで「断れません!」となっての審査?読書となりました笑。ゆるい!と思われたならすみません。
そんな偏った目線で読ませてもらったのがこの最終選考4作、
自身の人生の実体験ベースの文章でよかった!と思わされる作品群でした。
「気がつけば浅草最後の映写になっていた。」荒島晃宏
最終選考の4作中、最もノンフィクションらしい形を取りながら自身の当時の思い入れの乗せ方にこちらまで乗せられて一気に読ませてもらった。
自身を主人公にした記憶記録記述に作者の感情が乗せられていく様が、作者が意図してか意図せずにかのキャラ表現になっていることも面白い!
「気がつけば無職になっていた。」薫
文章表現や技術の高さに驚く!心蝕まれていく主人公に読み手まで一緒に壊れていく感じを体感。狂気混じりの切実で滑稽な笑いをどう扱えばいいのかと揺さぶられる面白さ!表現者と表現されたものの距離が冷静に取れてる……。
古書みつけ「文学賞」なら、これです!
「気がつけば三十九年間無職だった。」難波ふみ
作者自身のキャラ度の高さに圧倒された。好き!
手書きの原稿用紙での投稿も含めて、作者と作品中の主人公の距離感に目眩すら覚えた。読んでる間、訳のわからない笑いが収まらず……。
これ、たぶん「表現したい」「伝えたい」って根本の衝動に嬉しさを感じさせられたんだと思います!
「気がつけば生保レディになっていた。」忍足みかん
なにより登場人物たちのキャラの体温が伝わってきました!
実在のモデルを考慮した上で本心で書く、書けるか?部分の押し引きも推し量りまでも楽しめる。いまを生きる心優しき人たちの弱さと、それでも自分は善人でありたいという人間の普遍的なテーマまで垣間見ることができました。読後感もいい。暖かみと寛容で包み込むキャラ造形と空気感、実話なのに小説のようになっている他者描き込みの構成もお見事!
長文を読む機会がない人たちにまで届けることのできる文章だと思います。
漫画家・新井英樹
本橋信宏(著述家)
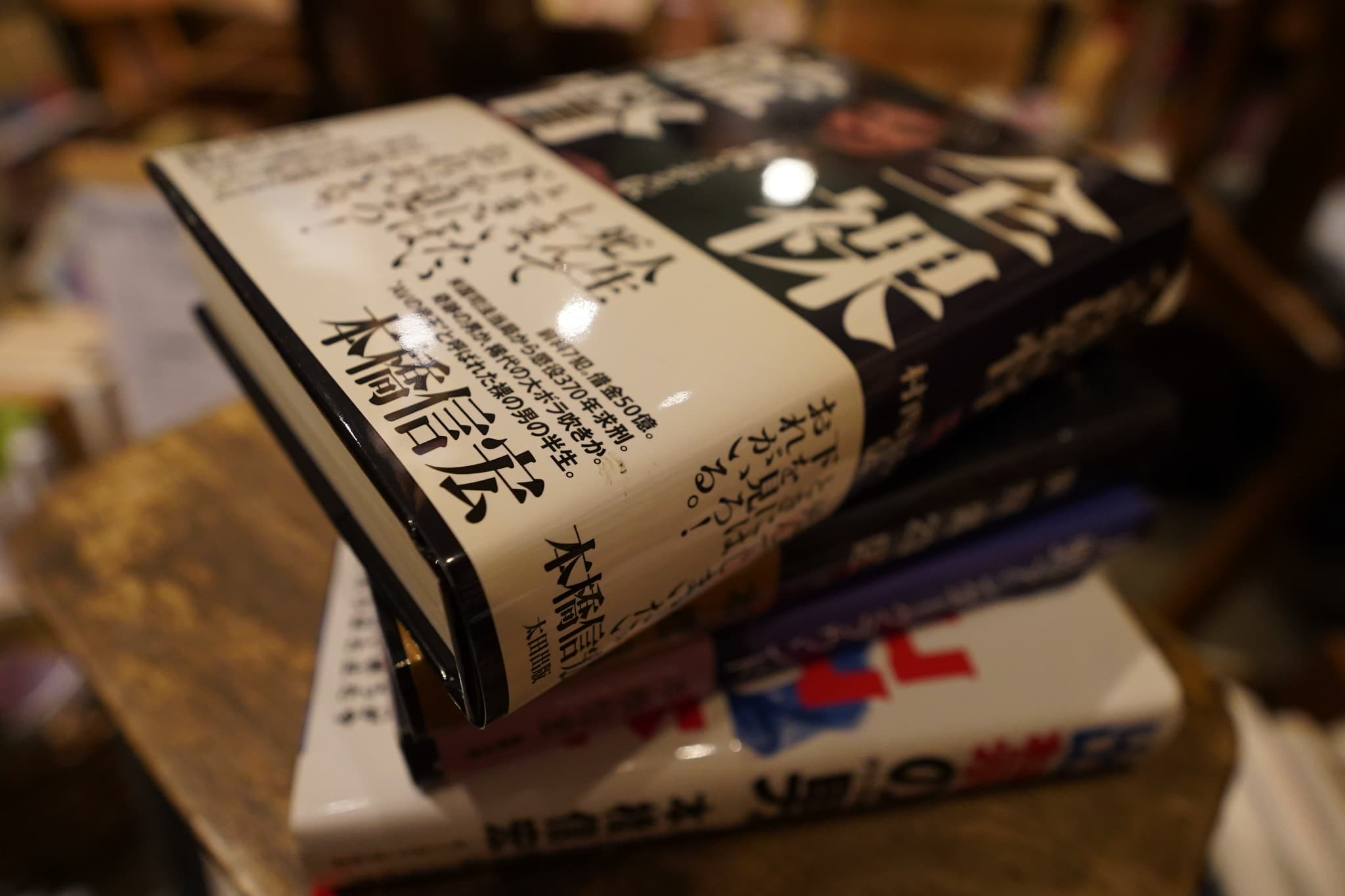
小説の駄作は掃いて捨てるほどあるが、個人の半生に駄作は無い。
その時、その場所で、そのことを体験していたのはあなたしかいない、究極のオリジナルであり、つまらないわけがない。
第1回「古書みつけノンフィクション賞」は、「気がつけば○○になっていた。」というお題を提示した上での公開公募という極めて珍しい賞として出発した。
はたして期待以上の応募作が集まるだろうかと危惧もしたが、結果的にはお題を提示したことは大正解だった。
「気がつけば○○になっていた」の○○に、これだけ多くの方々が関心を示し、自身の○○を埋めてきた。
最終候補にあがった4作品はどれも読み応えたっぷりの佳作ぞろいだった。
「気がつけば浅草最後の映写になっていた。」荒島晃宏
荒島晃宏さんの「気がつけば浅草最後の映写になっていた。」は、一度は自殺まで考えた男が、転職し浅草の映画館で8年間映写技師をつとめてきた話である。
映画館の舞台裏をここまでリアルに描写したものはそうあるものではない。
興味深いエピソードが無数、ある。
旧作上映会で最も客の入りがよかったのが、フォーリーブス主演,「急げ!若者」(1974年上映)だったという意外な事実。劇中でフォーリーブスの北公次がヤクザに脇腹をドスで刺され、苦悶し、殺されるシーンは当時評判を呼び、ヤワな青春歌謡映画とは一線を画す隠れた名作だった。演者の北公次も、いつか私に「あのころはいつ死んでもいいと思っていた」と打ち明けていたように、スクリーン上からも情念が伝わるのだろう。DVD化されていないこともあって、こういう隠れた名作は半世紀近くたっても客を呼べるのである。
映画館の壁にいくつも残るコーヒー色した欲望の染み。書き手が突きとめたもう一つの臭いの元は、当事者でしかつかめない事実だろう。
本作の書き手によって、映画の舞台裏を描くジャンルがさらに確立されたら僥倖である。
「気がつけば無職になっていた。」薫
「気がつけば無職になっていた。」は、コールセンターのオペレーターになった薫さんの日々を綴ったもの。
<目の前にある電話機のランプが、ずっと赤く点滅しつづけていて、早く電話を取れ取れと言っている。>
名文である。冒頭から引き込まれる。
クレーム、暴言、怒鳴り声にさらされるオペレーター。50人の同期が2年後には5人しか残らない。
薫さんの資産はゼロ、両親は離婚、父は新興宗教に入信,母は別の家庭をもっている。
薫さんの居場所は一人暮らしのアパートだけだ。
そんな彼にとって、唯一生きる糧になっているのが、100人以上いる女性オペレーターのおっぱいである。
ニットやセーターの胸の膨らみについ視線がいってしまう。
<誰も僕におっぱいを見せてはくれない。
目の前を何人かの女性が通り過ぎていった。
みんな服を着て、おっぱいを隠している。>
高名な作家だったと思うが、美しい女性を見ても、彼女が自分の人生とまったく無縁の存在であることに言いようのない虚しさを感じた、という記述を思い出した。
本作におけるおっぱいは、それをはるかに上回る衝撃であり、切実である。
乳房は本来母乳を製造する神聖な器官であり、古来から乳房は女性美と母性の象徴として彫像や絵画のテーマになってきた。
その一方、乳房は男たちの性欲の対象として存在している。
服の上から盛り上がる乳房をむき出し、揉み、吸い、しゃぶる男がいる、この悔しさ!
聖と俗を併存させるおっぱいは、男に夢と焦りをもたらす罪な存在でもある。
いっそ、本編のタイトルを<気がつけばおっぱい星人になっていた。>にしたほうが、注目度は飛躍的に高まり、読み手はまっさきに手に取っただろう。
読んでもらうにはそれくらいのケレン味も必要なのだ。
書き手はうつ病になり、無職になった。
孤独のなか、公園の桜に無限の生命を見つける。欠けているのは、桜を隣で一緒に見る誰かだ。
最終候補作のなかでもっとも手練れであり、ノンフィクション・小説の垣根を越えた書き手になる予感がする。
「気がつけば三十九年間無職だった。」難波ふみ
難波ふみさんの「気がつけば三十九年間無職だった。」は、意表を突くタイトルである。予定調和として、○○には現在の職業が入るものだと思っていたが、39年間無職という、不変を題材にした。すごい。
幼いころから精神の不調に苦しむ。
きっかけは父親の水虫だった。
伝染する汚らしいものと思い込み、以後、心のこだわりが強くなる。
母との折り合いがわるくなり、しばしば取っ組み合いになる。
精根尽きた母から「産まなきゃよかった」という決して言ってはいけない言葉を投げかけられ、文子さんは自己肯定感ゼロになってしまう。
<私は完全に混乱していた>
姉に噛みついたり、殴りかかったり、壁に頭を打ち付けたり。
<最終的に父を殺さなければいけない>
ここまで追い詰められる。
アルバイトをしようとするが、いつも面接で落とされる。
転機が訪れたのは30代に入って、学校に通う気になってからだった。
31歳、定時制高校に合格。
精神の不調に付き合いながら、登校する日々。
担任との面談では、担任から欠点ばかり指摘され、呆然となる。
私も中学1年のときの親との三者面談で、教師は励ましたつもりだろうが、こちらのコンプレックスを親の前でほじくりだされ、気が遠くなりかけた記憶がある。
本作の文子さんは、悔しさをバネに絶対卒業してやる、と心に誓った(偉い!)。
そして3年間、無欠席で卒業。
だが実社会は一度も就職経験の無い30代半ばの女性に厳しかった。
本作品は、心のアップダウンをみずから分析し、綴ったもので、これほどマイナス面の精神状態を明け透けに綴った文章は空前にして絶後だ。
私は本作が受賞してもいいと思った。
こんな立派な作品が書けるのだから、一度も就職できなくてもまったく問題ない。
「気がつけば生保レディになっていた。」忍足みかん
受賞作は忍足みかんさんの「気がつけば生保レディになっていた。」になった。
作者はすでに自著があるエッセイスト/漫画原作者である。
生命保険会社の営業体験をもとに書き下ろした本作は、骨太の作品に仕上がり、ドラマ化の可能性すら感じさせる。
冒頭、仕事に疲弊し、東武線のホームで飛び込もうとする。
<もう、死のうと思う。今日が私の命日になるであろう。>
会社に行きたくないという一心で、飛び込もうとする。心のありようがリアルな告白体で迫ってくる。
私は最近、目撃してしまった中央線での飛び込み現場を思い出してしまった。
本書ではカウントダウンしていざ飛び込むとした直前、足が止まる。
<自殺・・・・って死亡保険出たっけ>
仕事人間を揶揄する、強烈なオチ。
その一方で、<死んだら友達とカラオケに行ったり、ネコを撫でることもできなくなってしまう。死ぬってそういうことだ。悪いことから逃れられるけれど、いいことも全て手放さなくてはならない>ことに気づく。
<死相浮かんだ顔の資格証>をぶら下げて、仕事がはじまる。
担当地域に配る自己紹介チラシに、趣味がプロレス、特技がドラムと書いたところ、上司からお客さんウケするように、お菓子作りとフラワーアレンジメントに変えさせられる。
保険会社の裏側が暴露されているのだが、コミカルな味付けになっているので、救いがある。
職業の舞台裏を本人が綴った読み物が多々あるなかで、本書の存在感は際立っている。
この書き手はエンターテイメント的な才能から将来、小説に転じるのではないか。
最後に……
ノンフィクションはよくサッカーに例えられる。
野球やラグビーとは異なり、サッカーは人間にとって手という便利な武器が封印されている。
手=フィクション。
書き手はつい手を使いたくなる。
でもここはぐっと堪えて足だけでやらなければならない。だから苦労もあるし、読み応えがある。
今回のW杯のビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のように精密な判定をした場合、果たして手は使っていなかったかどうか。
1986年W杯、マラドーナがつい手でボールを触りゴールになった”神の手”があった。ヘディングなのかハンドなのかマラド-ナが試合後のインタビューで聞かれたとき、「神の手が触れた」と答えた。
サッカーの天才、神の子であるから、世界も受け入れた。
ノンフィクションも実は神の手が存在する。
マラドーナクラスの書き手に許されることなのか、悩ましい問題である。
著述家・本橋信宏
編集部より
御三方による講評、イチ編集者としてだけでなく、人生を生きていくうえでもとても参考・勉強になるお言葉でした。いまだに最前線でご活躍されているにもかかわらず、ご協力いただき本当にありがとうございます。皆様の今後のご活躍を、ファンとして、読者として、楽しみにしています。
最後までお読みいただいた方は、「古書みつけ(気がつけば○○)ノンフィクション賞」がどんなものかはご存知かとは思いますが、賞創設の経緯がわかる募集要項も置いておきます。第2回も応募できるように、応援よろしくお願いします。






